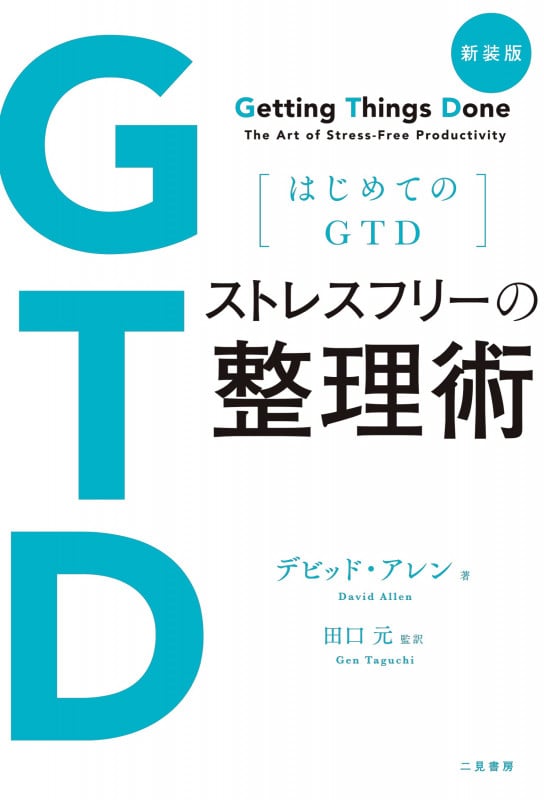2025-06-26 14:07
この話は、goccy/go-yaml 作者のgoccyさんと、YAMLの話を…止めない! という私のポッドキャストエピソードでも話した内容だが、口頭では説明が難しかったり、上手くまとまってなかった部分もあったので、補足的にエントリーを書いた。ポッドキャストでは裏話的な話やgoccyさんの生の意見も聞けるので、そちらも是非聞いてみて欲しい。
GoのYAMLライブラリとそのアーカイブ事件
GoのメジャーなYAMLライブラリには大きく以下の2つがある。
他にもYAMLライブラリはいくつかあるが、実態は、gopkg.in/yaml のラッパーであることがほとんどだ。例えば、github.com/ghodss/yaml や sigs.k8s.io/yaml 等。
gopkg.in/yaml は k8sやdocker compose内部でも使われている世界的に標準的なライブラリで、我々ソフトウェアエンジニアを支えている重要なライブラリと言える。そして、その開発リポジトリが正式にメンテナンスを停止し、アーカイブされる という事件があり、乗り換え先選定やメンテナンス継承等に関わる色々な動きが起きている。
アーカイブの影響
直ちに問題はなく、大事になっていない。ライブラリとしては利用可能なままだし、そもそも、gopkg.in/yaml のメンテナンスは実質的に大分前から止まっていたようなものなので、状況が大きく変わったわけではない、という見方もある。
ラッパーライブラリが多く存在するのもそのためだ。足りない機能やGoらしくないインターフェースをラップするために、ラッパーライブラリ経由で gopkg.in/yaml を操作する使い方がされている。YAMLの仕様は余りにも膨大であるため、イチからライブラリを実装するのは多くにとって現実的ではないという話もある。
とは言え、アーカイブされたライブラリに依存するのは長期的には不安定なので、乗り換え先を選定するか、既存のソースのメンテナンス継承を検討する必要がある。
そこで、有力な乗り換え先として注目されているのが goccy/go-yaml である。
2つのYAMLライブラリの比較
私は元々、goccy/go-yaml を好んで使っていた。そっちの方が使いやすく、品質も高いと考えていたからだ。作者のgoccy(五嶋)さんに対する信頼度が高いことも後押ししている。
2つのライブラリの簡単な比較は以下。
gopkg.in/yaml
古く(2011年)からあるGoのYAMLライブラリ
Cで書かれたlibyaml をGoに移植したような作りになっている
移植なので、libyaml実装に引っ張られた作りになっている
変数名や内部のインターフェースなど
libyaml自体が歴史があるプロジェクトなのでソースコードの統一感に欠ける部分も
goccy/go-yaml
後発(2019年)のYAMLライブラリ
YAMLの仕様を元に、Go向けにスクラッチで実装されたライブラリ
Goらしいコード・インターフェースで書かれている
ライブラリ利用者からしたインターフェースも自然で使いやすい
若いプロジェクトであることもあり、メンテナンスの統制が取れており、ソースコードの統一感が高い
YAML Test Suite のスコアも、gopkg.in/yaml よりも高い
実装をもとに作られたgopkg.in/yamlと、仕様をもとに作られたgoccy/go-yamlとアプローチが異なるのが面白い。開発の世界では良くある話でもある。
個人的には、goccy/go-yaml への乗り換えが進んでいくのだろうと思っていた。gopkg.in/yaml はそもそもメンテナンスに困っており、引継先なども模索した上で、それが難しいと判断してアーカイブされたのだろうから、今後引き取り手が現れる可能性も低いと思っていた。
ただ、goccy/go-yaml も個人プロジェクトではあるし、gopkg.in/yaml とのインターフェースの差異もあるため、乗り換えコストを払うことが見合うかどうかは様子見されている雰囲気も感じる。
そして、ここで、(あまり注目されていないが)大きな動きがある。YAML本家による、gopkg.in/yaml のメンテナンス継承である。
YAML本家によるメンテナンス継承
YAMLオーガニゼーション はYAMLの総本山であり、YAMLの仕様に加えて、LibYAMLやPyYAMLの実装、YAMLテストスイートなども公開・開発・管理している。YAML自体がPerl出自の技術であることもあってか、Perl6の実装も公開している のも面白い。そこが、gopkg.in/yaml のメンテナンスを引継を計画して進めている。そのリポジトリが以下だ。
(ちなみに、元々の gopkg.in/yaml のリポジトリはgithub.com/go-yaml/yaml なので、仕方がないのだが、紛らわしく、説明に苦労する。)
これは、客観的に見たら悪くない話ではあるだろう。メンテナンスに困ったOSSの受け皿として、このようなオープンな団体が手を挙げるのは良いことだ。ただ、リーダーシップ不在のまま引き取られたOSSが、結局放置される事例は多い。「墓場」の様な揶揄がされることもある。
gopkg.in/yaml の保守性の悪さからメンテナンスに苦労していた現実もある。そういう「死にかけている」ライブラリに対して無理に延命措置を講じることが本当に良いことなのか、という話もある。gopkg.in/yamlがその性質上、Goらしくないコードになっていることや、YAML本家のチームにGoのエキスパートがいなさそうなのも不安要素である。
この継承に関する議論は、CNCFのSlack の #go-yaml チャンネルで行われており、誰でも閲覧可能だ。CNCF内で議論されているというのが面白い。
ただ、最近のCNCF Slackのプラン変更 により、90日以上前のメッセージが閲覧できなくなるので見たい方はお早めに。該当チャンネルは、4/25作成のチャンネルなので、今ならまだ全部のログが読める。
goccyさんとYAML本家との対話
goccyさんも上のSlack上に投稿し、議論がなされている。YAMLの大本の作者である、Ingy döt Net さんが精力的に議論に参加していてアツい。
ここで、出てきた面白い観点としては、gopkg.in/yaml はLibYAMLの移植であり、Goらしいコードになっていないことが彼らにとって寧ろ好ましいという点だ。
これは言われてみれば無理もない話だろう。彼らは、LibYAML, PyYAMLも同時にメンテナンスしているわけで、go-yamlも含めて、それらが似通った実装になっている方がメンテしやすいというのは道理だろう。Goに詳しい人がいないから尚更だ。
そして、もう一つの観点として、「仕様が正か。実装が正か」というソフトウェア開発で頻出の話がある。彼らは、YAMLの仕様も、汎用的で網羅的なテストスイートも公開しているので、元々は仕様を正にすることも考えていたのだと思う。ただ、実際はLibYAMLやPyYAMLの振るまいが事実上の標準仕様となっていることを受け入れ、その方針で進めているようだ。だから、尚更、gopkg.in/yaml の実装がLibYAMLに近いことが好ましいという話になる。
実際、YAML仕様の記述には曖昧な点があり、テストスイート自体が正しいか、という話もある。
ちなみに、gopkg.in/yaml のテストスイート網羅率は73%であり、goccy/go-yamlは88%である (2024年12月時点 )。そもそも100%を目指す様な者でもなく、その必要性も疑わしいという話もある。
私は、YAMLのテストスイートが網羅されている実装は存在しないと認識していたが、実は2020年に、本家が全てのテストケースが通る参照実装を公開していた事を今回の議論の中で知った。そして、それを参考にテストスイートを網羅するライブラリも少ないながら出てきているとのことだ。
https://github.com/yaml/yaml-reference-parser
それと同時に、この参照実装は実用性に欠け、彼らがメンテナンスしているPyYAMLやLibYAMLも意図的に仕様から逸脱していて、テストスイートを網羅していないことも議論の中で明かしている。
現実問題としては仕方ないとも思うが、仕様から実装を進めていたgoccyさん的にはびっくりする話だっただろうが、その辺りの公式のスタンスが今回知れたのは良かったとは思う。
KubernetesのYAMLライブラリの移行
ちょうど本日、6月26日、Kubernetes本体から、gopkg.in/yaml の依存がドロップされ、新しい go.yaml.in/yaml (yaml/go-yamlのライブラリ名) へ移行するpull requestがmasterに取り込まれた。
Drop usage of forked copies of goyaml.v2 and goyaml.v3 by dims · Pull Request #132357 · kubernetes/kubernetes
現実問題としては、インターフェースやコードベースが同一の後続ライブラリに移行するのは丸い選択肢だとは思う。この新しいyaml/go-yaml はKubernetesが正式に採用することになり、CNCFも巻き込んで議論されているので、メンテナンス体制の不安もある程度払拭されたと言えるかも知れない。
私Songmu個人的には、引き続き、goccy/go-yamlを使い、推していきます。
おまけ: yamlscript
今回の議論の中で、YAML作者のIngy氏は現在yamlscript という恐ろしい名前のプロジェクトに積極的に取り組んでいることも分かった。YAML愛が凄い。Ingy氏についての話や、yamlscriptについては、冒頭にも書いた、YAMLの話を…止めない! というポッドキャストエピソードで話しているので是非聞いて欲しい。
また、今回のSlack上での議論については、その半公開の性質上引用は控えた(多分やっても問題ないとは思うが)。議論を見たい方は、Slackに参加 して #go-yaml チャンネルを覗いてみて欲しい。6/4~6/6辺りの議論なので、8月一杯くらいでアーカイブが消えてしまうのでお早めに。
2025-06-26 00:02
Songmu/action-create-branch
READMEにも書いてあるが以下のように使う。これは、指定ブランチがあれば作るし、無かったら何もしない簡単なGitHub Actionだ。分岐元指定のrefにはブランチ名、タグ、コミットハッシュを指定できる。refは省略可能でデフォルトではgithub.refを使う。
- uses: Songmu/action-create-branch@v0
with:
branch: feature/new-feature
ref: main
何故作ったか
先のエントリーの、action-push-to-another-repository のフォーク元には、元々、create-target-branch-if-needed という、指定ブランチがなかったら作るオプションがあった。しかし、私がフォークしたものからはそれを削除した。コードの複雑性が増してしまっていたし、その機能を内包する必要性も感じなかったからだ。
ただ、一時ブランチを作って、そこにpushするユースケースは確かにあるだろう。であれば、前段に、ブランチがなかったら作るというステップを定義すれば良い。
そういう、単純にブランチを作るだけのGitHub Actionはきっとあるだろうと思ったが、案外良い物が見当たらなかった。具体的には、分岐元のrefにブランチ名、タグ、コミットハッシュを柔軟に指定したいが、それができるアクションを見つけられなかったので、作った。
APIで操作するので、事前にcheckoutする必要がないのも嬉しいポイント。
action-push-to-another-repositotyとの組み合わせ
リポジトリのREADMEにも追記 したが、以下のように使えば良い。
- uses: actions/checkout@v4
persist-credentials: false
- name: Create branch if needed
uses: Songmu/action-create-branch@v0
with:
repository: 'owner/dest-repo'
branch: 'new-feature'
ref: develop
- name: Push to another repository
uses: Songmu/action-push-to-another-repository@v2
with:
destination-repository: 'owner/dest-repo'
destination-branch: 'new-feature'
こちらの方が、1つのアクションに変にオプションを増やすよりも明確で分かりやすい。この様に、シンプルな部品を作りシンプルに留めること、それらを上手く組み合わせて使うのがソフトウェア設計全般で大事なことの1つだ。
実際、action-push-to-another-repositoryのスクリプトは50行程度だが、action-create-branchは133行と実はこっちの方が分量が多くなっている。なので、ブランチを作る処理はやはり内包したくない。
ちなみに、aciton-push-to-another-repositoryのコード行数が比較的少ないのは、コミット処理をsuzuki-shunsuke/commit-action に委譲しているからだ。
また、action-create-branchのコード行数が比較的多いのは、指定されたrefからコミットハッシュを解決する処理がそこそこ複雑だからだ。それを今回はGraphQL APIを使って、一撃でcommitハッシュを取得するようにしてあるのが面白ポイントなので、興味ある方はコード を見て欲しい。
このアクションの開発ではClaude Codeに大半のコードを書いてもらった。便利ですね。
2025-06-24 03:16
あるリポジトリの一部または全部を別リポジトリのルートなりサブディレクトリにpushしたくなることがたまにある。一般的にもニーズがありそうだが、ちゃんとメンテナンスされているモノが見当たらなかったので、以下に公開した。かなり便利。
これはイチから作ったわけではなく、cpina/github-action-push-to-another-repository をforkしたものです。このfork元は、私も使っていたのですが、メンテナンス停止が宣言されており、signed commit対応などもされなさそうなので新たに開発することにしました。
そう、signed commit対応 が今回公開したGitHub Actionの目玉です。actions/create-github-app-token を使ってトークンを発行し、そのトークンでsigned commitするという仕組みです。
ユースケース
privateリポジトリで作成したコンテンツを公開リポジトリにプッシュしたり、あるリポジトリの内容を別リポジトリのサブディレクトリにpushするなど、色々活用法は考えられますが、私のユースケースを以下に紹介します。
プライベートリポジトリでポッドキャストのコンテンツを事前に作成しておき、公開時に公開リポジトリにpushさせている。これは、リポジトリ丸ごとsyncしています。
詳細は Workflow file を参照ください。
Zenn のGitHub連携は、ある人やオーガニゼーションの複数の記事や本を1つのリポジトリでまとめて管理する仕様になっている。これを、もともと単独リポジトリで管理していたgithub-handbookと連携するために、ghq-handbookのjaディレクトリの内容を、zenn.devのbooks/ghq-handbookディレクトリにpushさせている。
詳細は Workflow file を参照ください。
まとめ
今回の目玉である、signed commit対応ですが、これは、suzuki-shunsuke/commit-action を内部で使わせてもらって楽させてもらいました。ありがとうございました!
結構便利だと思うので是非使ってみてください。
2025-06-22 00:23
フリーランスになって、複数の案件を同時に進める必要が出てきたこともあり、タスク管理方法を見直した。何なら手法やツールも自作してしまおうと考えた。何かを始めるときに、まず道具から作り始めてしまうのは自分らしい振る舞いで面白い。
これをTaskMD Shelfと名付け、仕様を公開した。
https://github.com/Songmu/TaskMD-Shelf
これは、1 タスク = 1 Markdownファイルとして管理する手法。各ファイルはTaskMDと呼び、それに最小限のメタデータ設計と運用ポリシーを定めたもの。単純なアイデアで、類似の方法でやっている人も既にいるだろう。
既にこれでタスク管理をしていて上手く回っている。ObsidianのDataviewプラグインがとにかく役に立っているのだが、その辺りの話は別途。
怠惰な自分でも続けられる手法
個人的に、強すぎる制約があるタスク管理手法は長続きしづらく、続けていてもどこかで躓くと途端に折れて諦めてしまうことが多かった。
なので、怠惰な自分でも続けられるシンプルなタスク管理 を目指した。
具体的には「今やらなくて良いことは積極的に棚上げする。ただし、見直し日 は必ず定める」、という「積極的棚上げ 」を基本戦術とした。
個人タスク管理に求めること
個人タスク管理に求める事は以下である。
今、やるべきことを絞って明確にしたい
関わっているタスクを失念しないようにしたい
半年後のタスクも、それまでは忘れておきながら適切に思い出したい
アイデアややりたいことも思い出せるように全て記録しておきたい
GTD(Get Things Done)インスパイア
古来から提唱されている優れた手法であるGTDが目指す所も近い。実際GTD本を改めて読み返して、かなり参考になった。ただ、以前、GTDの実践を試みたこともあったが、その時にネックだったのが、とにかくタスクリストのメンテナンスに労力がかかることである。
「ネクストアクション」「備忘録ファイル」「プロジェクトリスト」「いつかやるリスト」etc., 確かにどれも重要だ。これらを「週次レビュー」で、しっかり定期的に時間をとってメンテナンスする必要がある。そして、週次レビューを怠ると、途端に本当に一瞬でシステムが崩壊するのだ。なので長続きさせられなかった。
ベースの哲学は優れているので、ツールや仕組みを工夫して手間を減らし、同様のことを実現したい。
なので、TaskMD Shelfでは全てのタスクをセマンティックプロパティを付与したテキストファイルを使ってデジタルで一元管理する。フィルタやビューを活用して、複数のリストのメンテナンスを不要にする。
積極的棚上げ戦術による自然なWIP(Work in Progress)制限
WIP制限はとても重要だ。そして「言うは易し、行うは難し」の典型例でもある。その制約を守れれば良いが、現実的にはとても難しい。これも心を折ってしまうような強すぎる制約になりがちである。
WIP制限は理想状態であり、そこに向かっていける仕組みが重要である。WIP制限を課すのではなく、結果としてWIPが制限されている状況を作るのである。
ここで「積極的棚上げ 」戦術である。今日やらないと決めたことは「棚上げ」して、机の上(実行中リスト)から片づける。ただし「見直し日 」を必ず設定して、その時に再開するか、再度棚上げをするかを決める。それだけのことだ。
レビューやメールの返信待ちなど、待ち状態のタスクも棚上げする。ここで重要なのは、それらにも必ず「見直し日」を設定することだ。これによって適切に催促できるし、有耶無耶になって立ち消えてしまうことを防げる。
TaskMD Shelfでまず実現できること
これらを踏まえて、TaskMD Shelfでは以下のようなことが実現できる。
小さく始められること
とりあえず一つのTaskMDを作るところから始められる
タスク登録に手間がかからないこと
最低限、タスク名たるファイル名とステータスだけ決めれば良い
全てを保管しておけること
タスクだけでなく、アイデアややりたいことも全て雑に記録しておける
こまめに整頓できること
大掛かりな棚卸しをせずとも、空いた時間に順次見直しができる
これらのTaskMDファイル群を管理するために自分で自由にツールを作っていくことができるが、取り急ぎ、ObsidianのDataviewプラグインが非常に便利で、これを使って進行中タスクリストなどのビューを作成している。
プレーンテキスト指向
TaskMD ShelfはNotionのデータベースなども使うこともできる。様々なビューも作れるのでとても便利だろう。
しかし、プレーンテキストファイル群で管理することをお薦めしたい。それがまさしく、タスクの棚たるTaskMD Shelfである。
Obsidian CEOであるSteph AngoのFile over app の哲学にとても共感しているが、データフォーマットが決まったファイルが手元にあることはとても自由だ。IndieWeb の思想に通じる物もある。個人が一生に抱えるタスクのデータ量なんて大したことはない。自前で充分に管理できる量だ。Gitを使えばバージョン管理もできる。
AIに支援してもらう
自分の管理下にTaskMDを置けば、AIに学習もさせやすく、支援も受けやすくなる。
今回、TaskMD Shelfを作るにあたってまず仕様をまとめたのは、根幹となる基本のデータ設計をしっかりやるSoR的な発想もあるが、それと当時に、AI支援を受けやすくすることや、ツールを作ってもらいやすいようにするという狙いもある。実際、このTaskMD Shelfを操作する為のCLIやMCPもClaude Codeに書いてもらっている。それらは公開するつもりである。
将来的には、TaskMS Shelfの内容を学習したAIが、次にやると良さそうなタスクを提案してくれたり、滞っているタスクのケツを叩いてくれたり、もう実現が不可能そうなタスクをそっと諦めさせてくれたりすると嬉しいと思っているし、それが出来るようになるとも考えている。
まとめ
しかし、仕様をまじめ腐って書いたらかなりの分量になってしまった。恐らくタスク管理手法考案者全員が「省力で長続き出来る方法」を当初は志向、模索しながらも、結局重厚になってしまう歴史を辿ってきたのだろうな、というのを体感した。
今回TaskMD Shelfを考えるに当たって、自宅にあるGTD本を含めたタスク管理手法の本を読み返すとともに、新たに気になっていたタスクシュートの本も何冊か読んだ。改めて非常に参考になった。タスクシュートからは一日にやることを絞ることや、実際に「できた」ことを記録すること、そこから成功体験を積み重ねることが重要だと再認識した。
その辺りのリサーチや、実際にTaskMD Shelfを運用してどうだったかは、大吉祥寺.pm 2025 で話したいのでプロポーザルを提出する予定です。
提出しました → 怠惰で持続可能な、自由なタスク管理 - TaskMD Shelfの実践
2025-04-11 15:27
2025年4月より、所属していた株式会社ヘンリー は非常勤となり、フェローという肩書きを拝命しました。フェローとしては技術広報や採用広報の支援を中心に活動します。
ヘンリー理想駆動ラジオ というポッドキャストを始めたのもその一環で、今後書き起こしなども出していく予定です。
背景としては、プライベートの状況や色々もあってフルタイムで働くのは辞めようと考え、そういう状況でVPoEの責務を果たすのが難しくなったというのがあります。元々は退職予定でしたが、パートタイムで在籍を残させてもらうことになりました。
独立
元々個人事業主ではありましたが、フリーランスとしても正式に(?)独立となります。しばらくあまり稼働時間は増やさず、自分がやりたいことにもう少しフォーカスしたいとは思っています。
やりたいこととしては、今、本を書いているのですが、そういう文筆業だったり、OSSやBlog、ポッドキャストを含めた発信や創作活動を、自分の仕事の中心にできないかと模索していくつもりです。
自分でプロダクト作ったり事業を始めたりする可能性もあるとは思っていますが、まだノープランです。
企業への支援業など
現状、ヘンリー社の他に、元々、MOSH社の技術顧問 を務めていて、そちらも継続します。
他にも企業への支援業はお声がかかれば受けていきたいと思っています。ただ、ありがたいことにすでに何社かにはお声をかけていただいており、自分の仕事のペース的にも、そこまで急に何社も増やすことは考えていないです。
色々支援できることはあると思っていますが、私自身、器用貧乏というと謙遜が過ぎますが、出来ることは多いものの、あまり「コレ」といった売りを作ってきたわけではないので、やれることを整理したいとは思っています。その辺りは改めてアナウンスできればと思っています。
何にせよ、面白そうな連絡をいただければお話などはさせていただければと思っています。いただく連絡の量によっては捌ききれない可能性もありそうなので、その際はご容赦ください。
2024-12-17 01:09
今年もISUCONに参戦した。今年も無事に開催され、素晴らしい出題と運営で良かった。ありがとうございました。
いつものカラアゲネイティブなメンツで出ようと思っていたが、 @toricls さんが出場できなかったため、私が技術顧問を務めているMOSH社CTOの村井さんを無理やり誘ってチームを組んだ。と言うことで、今年のカラアゲネイティブは、 @motemen, @RyosukeIketeru, @songmu の3名。言語はGo。リポジトリはこちら。
https://github.com/motemen/isucon14
序盤の作戦会議
競技開始後、いつものようにmotemenがインフラ周りを設定している間に、村井さんと僕との二人でマニュアルとレギュレーションを読み合わせる。motemenも耳で参加
ここはなんだかんだで1時間くらいかかるが大事な工程
シミュレーター含めて細部まで良くできててビビった
細かくアプリを触らないと分からないボトルネックがあるという運営からのメッセージなのか?とか思ったけど、結果的にはそういうわけではなさそうだった
今回はアプリケーション部分の改善と仕様の調整がスコアに響いてくる点が新機軸で良かった
取り合えずレギュレーション読んで以下の3点が攻略ポイントだとあたりをつける
決済周りの冪等キーヘッダ対応
これは単純にやれば良いだけという話っぽい (実際そうだった)
通知の改善
最終的にマニュアルに書いてある通りSSE化まで辿り着けるのが理想だが、そこに行く前に潰すべきボトルネックが色々ありそう
マッチング改善
最後まで下二つの改善が課題になるので、そういう意味では分かりやすい問題だったと言えるかも
前半戦
まずは肩慣らしに簡単そうな冪等キーヘッダの対応 #10
初期実装のワークアラウンドクソコードに対するFIXMEコメントがリアリティあって良かった
マッチング処理のエンドポイントが定期的に叩かれてアクセスログを汚すのもイヤだったのでgroutine化 #12
マッチングエンドポイントを叩くプロセスは止める
念のため設定ファイルのINTERVALを3600にも設定した
if hostname != "ip-192-168-0-11" { と言うクソコードによりマッチングロジックが1台でしか動かないようにもしたこれらによって後のマッチングロジック改善がやりやすくする狙い
interpolateParams=true #17
goccy/go-json 投入 #18
3台負荷分散 #19
アプリケーションをisu01, isu02で動かしDBをisu03に移動
マッチングロジックはisu01でしか動かないように
しかし今や僕はISUCONでしかNginx.confを触らなくなってしまった
この頃合いに、motemenと村井さんがpt-query-digestを見ながらインデックスの追加だったり、テーブル構造の変更などをやってくれていた。
だいたい、前段のやるべきことは終え、後半戦は想定通り本命のマッチングと通知の改善かな、と言うところに至った。ただ、この時点で15時近くなっていた。てこずって時間をかけすぎたのでこのあたりもう少しスムーズにやりたかった。何はともあれ、通知周りの改善は他の二人に任せ、僕はマッチングの改善に取り組むことにした。
後半戦
当初のマッチングロジックがあまりにもひどかったので修正
とりあえず、chairs.is_occupied というカラムを追加し、配車中かどうか判別できるように
しかしこのステータス更新で苦しんだ
マッチング時に is_occupied = true にするのは簡単だったが、解除するタイミングがよく分からずてこずった
ライド完了時にフラグを戻してしまうと、椅子が完了通知を受けとる前にマッチングが始まってしまいエラーになる
完了通知のところでフラグを戻そうとすると、マッチング待ちが長くなりすぎてエラーになる
ここは根本究明できず、ライド完了時に、非同期で200msec遅らせてgoroutine内でフラグを戻すという酷いコードを書いて通した
これで少しスコアは上がった
ここで時間切れ
このロジックでは単に空いてる椅子が適当に選ばれるだけになっていて元のロジックと大差ない
ちゃんと近傍を割り当てる最適化に取り組みたかったのだが…
と言うことで、終了間際に回したベンチが通って、14,987点でフィニッシュ。順位は多分103位。
反省
良問で運営やポータルも快適で、コードも色々書けたので楽しかった
誘った村井さんも楽しんでくれたようで良かった
Goに不慣れな村井さんをもう少しフォローできれば良かった
motemenが苦労しているときにも、ペアプロするなりすればもう少し早くバグに気付けたかも
このあたりはmotemenがインフラ構築担当であることもあり、アプリの理解度が少し落ちると言う点も影響があったかも知れない
インフラ構築担当がコードも書く体制なら、インフラ構築後にマニュアル熟読担当が構築担当に問題概要をレクチャーする時間があっても良いのかも
何なら来年はインフラ構築担当を切り替えても良いのではないか
カラアゲネイティブチームは、結成初年度は僕がインフラ構築担当だったが翌年からずっとmotemenが担当しているし役割が固定化している
今年の構築はめっちゃ早くてトラブルもなくて熟練を感じた
いつものメンバーのスキルセットは近いので、それぞれの役割分担が固定化している今、それぞれがやっていることを棚卸しして他の人ができるようにする価値はありそう
マニュアル読みに時間はかけるのは必要だけど、その後の初速をもっと速くしたい
ISUCON用ツールを自作するのとかもやっても良いかもと思い始めた
これまで、僕が結成時に作ったものの注ぎ足し、注ぎ足しされた秘伝のMakefileを一枚持ち込むのみで戦ってきたが限界がある
アイデアとしてはスコアの記録とか、pt-query-digestやperformance schema, alp辺りの集計をいい感じにしてくれる君とか
一緒に組んでて、僕よりmotemenの方がISUCONに勝ちたい気持ちが強い感じがするので、来年はもう少しそこに協力したいかな
何にせよ来年も開催されることを期待しています
2024-12-16 00:25
この記事は pyspa Advent Calendar 2024 の14日目の記事です。この記事で言いたいことを先にまとめると以下になります。
日本の技術系アドベントカレンダー文化は独自の進化を遂げている
エンジニアに限らない広がりも見せている
良い文化だし長く続いて欲しいと思う
元の文化への敬意を忘れてはいけない
宗教色があるものだし、少なくともアドベント期間外に拡張しない方が良いと私は思う
長くこの文化を楽しむためにも
技術系以外のトピックでもアドベントカレンダーが作られることがありますが、この記事では便宜上それらも含めて技術系アドベントカレンダーと呼称します。
技術系アドベントカレンダー
日本の主に技術系のインターネット界隈では毎年12月になると、技術系アドベントカレンダーというムーブメントが発生します。ある技術トピックに対して、12月1日から25日まで複数人が持ち回りでブログを書くというのが基本的なスタイルです。
ニッチなトピックに対して一人でがんばって全部書くスタイル、技術以外のトピックのカレンダー、企業単位で社員持ち回りで書くなど、様々な派生を見せています。私が所属している株式会社ヘンリーも去年、今年と実施しています。
これは、お互い背中を押し合って、普段ブログをなかなか書く機会がない人がブログを書く機会になったり、結果として多くの有用なコンテンツがインターネットに放流されたりするので、良いイベントで、長く続いて欲しいと願っています。
技術系アドベントカレンダーの歴史はこれまでも多くの場所で語られていますが、今後この文化を長く続けるためにも歴史を知っておくことは有用だと思うので、改めて歴史をひも解きます。
原義の物理アドベントカレンダー
そもそもアドベント(待降節・降臨節)とは、11月末からクリスマスイブにかけて、キリストの降誕を待ち望む期間のことと日本語のWikipediaに書かれています。
そして、アドベントカレンダーとは、その期間に使う、ビンゴ的UIの日めくりカレンダー的アイテムです。それぞれの日付の扉を開けると、絵や聖書の一節、お菓子などが現れる仕組みです。カレンダーの開始日はその年のアドベントの始まりの日もしくはシンプルに12月1日、終了日は12月24日か25日のようです。これも、英語版のWikipediaに書かれていました。
つまり、降臨を待ち望む期間の日めくりのカウントダウンカレンダー的なアイテムであり、特に子供向けで毎日小さなお菓子が出てくるものが良く知られています。日本でも近年はカルディなどおしゃれな輸入食品を扱うようなお店で見られるようになりました。
つまり、そもそもは宗教的な催しでありアイテムなのです。
技術系アドベントカレンダーの萌芽
このアドベントカレンダーをモチーフに2000年に作られたのが、英語のPerl Advent Calendarです。これが恐らく技術系アドベントカレンダーの発祥です。2000年から始まったこの本家アドベントカレンダーがまだ今年まで存続しており、アーカイブも残っていることに感動を覚えます。
Perl Advent Calendar Archives
2000年から2004年にかけては、創始者のMark Fowler氏個人によるPerlモジュール紹介リレー形式になっていました。そして、彼が当初書いたAboutページ がまだ残っており、その冒頭が奮っています。
This goes along way to proving what I always say: I come up with the best ideas when I'm hung over.https://perladvent.org/2000/about.html
訳すと「これは私が常々言っていることを証明するものだが、二日酔いの時に最高のアイデアが浮かぶ。」と言った具合でしょうか。このページを読み進めると、London.pmの会合がその二日酔いの原因で、その勢いで翌日の昼休みにこのAdvent Calendarを作ったと書かれています。
それが、2024年まで継続していることは胸熱ですが、海外では他言語や技術コミュニティにその文化が輸出されることはあまりされていないようです。これは私の観測範囲の問題かも知れないのでご存知の方がいれば教えて下さい。
ちなみに私も2015年に "Perl and Redis " という記事を寄稿しました。お誘いのメールをいただいたときは大変嬉しかったので引き受けたことを覚えています。翌年も誘ってもらったのですが、それ以降残念ながら寄稿できていません。
日本への輸入
この技術アドベントカレンダーが日本のPerlコミュニティにより輸入されたのが2008年です。これも、ちゃんと当時のコンテンツが残っていて素晴らしいですね。
JPerl Advent Calendar 2008
記念すべき初日の記事は定数の展開 という記事で、サンプルコード含めて6行しかなく、何なら誰が書いたかすらも書かれていない、非常にシンプルなTipsの紹介記事です。
始まりの経緯はtokuhiromさんの技術的アドベントカレンダーの有用性について という記事に残っています。初年度は前日にアップした人が翌日の人を指名しながら、バトンを繋いでいく形式で、必然的に5分でさくっと書けるようなtipsが集まっていたようです。確かに毎日ちょっとしたお菓子が食べられるという原義のアドベントカレンダーともコンセプトがマッチしています。
バトン形式で繋いでいく方式も緊張感はありますが、その分全日埋まることは期待されていなかったように感じます。逆に案外初年度がちゃんと埋まってしまったというところでしょう。上記の記事内の寿司奢る云々も多分ネタだったのではないでしょうか。
実際、その後のエントリー形式になった2012のHacker Track の3日目で、gfxさんが体調不良により記事を落としています。
@__gfx__は病欠です
今では見られませんが、代理でgfxさんのアイコンがぐるぐる回るアニメーションが投稿され、コミュニティ内で楽しんでいたのを覚えています。当時はそういうゆるさがありました。
上で"Hacker Track"と書きましたが、2年目の2009年 ではHacker TrackとCasual Track、その他2トラック合わせて合計4トラック構成になりました。
私もこの2009年のCasual Trackの15日目に「PerlでEmEditorマクロを書こう 」という記事を初寄稿しています。Perlコミュニティに初めて参加できた喜びを感じたのを覚えています。
ちなみに、当時の記事投稿方法はCodeReposのSubversionリポジトリのコミット権をYappoさんから貰い、はてな記法で書いた記事をコミットするとサイトが更新されるという方式でした。
この記事のエントリのタイトルの通り、私は当時はWindows上のEmEditorでPerlを書いていました。しかし、TortoiseSVNで上手くCodeReposにコミットできず、焦って当日ヨドバシカメラにMacbookを買いに走り、セットアップして、なんとか記事のコミットに漕ぎ着けたことを覚えています。これが私にとっての初Macでした。これはもちろんWindowsやTortoiseSVNの問題ではなく、当時の私が何も分かっていなかったという笑い話です。
2010年は8トラック、2011年は9トラックとなり、この頃がPerlのアドベントカレンダーの最盛期と言えるでしょう。その後、独自サイトはやめて、2013年からはQiitaで記事を募る 形をとっています。
独自進化と定着期
これが日本では他の技術コミュニティに速やかに横展開され、すでに2011年時点でかなりの数が実施されていることが以下の記事に記録されています。
また、2012年にエンジニア向けナレッジシェアサービスであるQiitaにアドベントカレンダー機能 が追加され、同年に技術記事以外にも気軽に使えるアドベントカレンダープラットォームであるAdventar がリリースされたことにより、アドベントカレンダーの開催がとても簡単になりました。それが追い風となり、その後数えきれない程の技術系アドベントカレンダーが作られることになり、完全に独自の文化として定着して今に至ります。
今の技術系アドベントカレンダーは毎日ちょっとしたお菓子が出てくるというよりも、毎日ホールケーキが出てくるような様相を呈していますが、それも面白い変化です。ただ、力を抜いた昔のようなアドベントカレンダーもあっても良いと思っています。
上記2サービスは、日本の技術系アドベントカレンダーの発展に大きく寄与したと言えます。しかも、Adventarは @hokaccha さんの個人サービスです。彼はGitHub Sponsorを開けているのでご利用の方は是非スポンサーを検討してみてください。私は先程小額ですがスポンサーしました。
https://github.com/sponsors/hokaccha
文化の盗用への懸念
ここまで書いてきた通り、この技術系アドベントカレンダーは、元々宗教色のある物がアレンジされ、日本で独自発展しているものです。私はこれが文化の盗用(cultural appropriation)のような形で批判されないか少し心配しています。
私としては元々の文化が理解されて敬意が払われており、アドベント期間を有意義に過ごすためのアイデアというコンセプトを外さなければ問題無いと考えています。元々の本家の英語のPerlアドベントカレンダーがアドベント期間に開催されているように。
ただ、アドベント期間を外れているのにアドベントカレンダーを名乗るのは良くないと私は考えています。それは元の文化への理解に欠ける行為に感じるからです。
そういった一部の逸脱が行きすぎた結果、それが文化の盗用だという妥当な批判をされ「アドベントカレンダーという名前は適切じゃないからみんな使うのを止めよう」となってしまうかも知れません。それは、この文化が好きな私としては悲しいですし、そうなって欲しくありません。
この技術系アドベントカレンダー文化を長く楽しく続けるためにも、歴史や元のコンセプトの理解が大切だと思い、このエントリーをしたためた次第です。
2024-11-25 01:50
最近、Webエンジニア界隈で、共通項を感じる印象的な出来事があった。具体的には以下の2件。
ゆーすけべーがHonoを作ったこと
おぎじゅんさんが職業プログラマーに戻ってきた(きていた)こと
共通項はそれぞれ長めのブランクがありながら、ソフトウェアエンジニアリングの世界に戻ってきて一線級以上の活躍をしているということだ。二人とも僕と同世代かそれ以上の年齢でもある。これは勇気と希望をもらえることだ。
もちろん彼らの能力の高さゆえに第一線に戻ってこられたのかもしれない。ただ、どちらにせよ、別のことに興味があれば、職業エンジニアを離れて、フォーカスする期間があっても良いと言うことだ。能力不足ならなおさら中途半端になるよりフォーカスしたほうが良いとも言える。
それに多分戻ってこられる。ゆーすけべーの様に世界的エンジニアになるのは難しいにせよ、別に満足に働けるくらいには戻せるのではなかろうか。
技術は日進月歩で、キャッチアップを怠ると途端に置いていかれる不安があるかも知れない。でもそこにしんどさを感じ始めているのなら無理しないほうが良い。それに、そんな厳しい業界だったら新しい人が誰も参入できなくなって、消え去ってしまう。実際には優秀な若者が新たにどんどん業界に入ってきてくれている。
もちろん、若い人の方が我々よりも優秀であるという事実はあるが、経験や結晶性知能で勝っている部分もある。AIなどのテクノロジーに補助してもらえる部分も増えている。眼鏡がそうであるように。何より、いくらAIが発展しようと、ソフトウェアエンジニアは足りない状況が続くので、少ないパイを競って蹴落としあう必要はなく、寧ろ皆で高めあっていく必要がある。
人事になりました
私事ですが、10月から人事に異動しました。正式には「株式会社ヘンリー 経営管理部門 人事本部 VP of Engineering」というタイトルです。
私はなんだかんだでこれまで兼務ベースで約10年エンジニア採用やエンジニアリング組織開発にも携わっていて、知見やノウハウもあるのでフォーカスする期間があっても良かろうというところ。
今後はエンジニアとしての発信だけではなく、採用や組織的な発信も増やしていければ良いかと思っている。エンジニアとしての経験を活かし、人事関係のノウハウを抽象化してパブリックに公開するというのをもっとやりたい。
なので、今はプロダクションコードを書いていないが、またいずれコードを書く仕事に戻る気持ちは全然ある。今、どういう役割の帽子をかぶって、どこにフォーカスするかが大事。必要に応じて柔軟に帽子をかぶり変えて行きたい。
冒頭の話もあって、いつだって戻ってこられる安心感が強まったから別のところにフォーカスしようと思えたのもある。元々、プレイングマネージャー否定派ではあった。プレイングマネージャーやってた時期も長いけど。
家族や子育てにフォーカスしたって良い(当たり前)
別に子育てに限った話ではないが、結婚や子育てを機に、以前ほど趣味のエンジニアリングに時間や情熱を割けなくなっていることを不安に感じている人が結構見られる。私も感じることはある。
でも別に働くことや趣味のエンジニアリングを緩めて、家族や子育てに集中する時期があっても良いと思う。それは間違いなく人生を豊かにする。私自身も最近それを強く感じるようになった。自己正当化バイアスかもしれないが、そんなバイアスなら歓迎である。
これも当たり前だけど、家族や子育てに比重を置くのもあくまで個々人の選択であって、別のところに目を向けてみたって良い。
怖いのは情熱が枯渇すること
結局怖いのは情熱が枯渇すること。例えばエンジニアリングへの情熱が以前より失われているとかそういったこと。枯渇させないためにも、休んだり、気分転換で別のことをやったり、別のことにフォーカスしてみたりすることが大事。
何かにフォーカスすることで情熱が生まれることもある。そして何かにフォーカスしないとなかなか情熱は生まれづらい。その結果として、エンジニアリングへの情熱が失われたとしても、他のことに情熱を持てればそれでも良いとも言える。中途半端に色々なことをこなすことに終始して、消耗してしまうのが巧くない。
自分の人生のリソースには限りがあり、やりたいことを全部やれないもどかしさを抱えながら生きる人も多い。私もそう。寧ろそういう人が幸せと言える。そういう中でフォーカスポイントを変化させながら情熱を持ち続けることが幸せに生きるコツなのだと思う。選択と集中である。
「選択と集中」における選択の重要性
「選択と集中」はよく言われる言葉で、集中・フォーカスすることの大事さはよく説かれるが、それと同じように選択できることも大事である。
歴史上の選択と集中の失敗例として、発展途上国が一部の一次産品に生産を集中した結果、余計貧困が進んだ、と言う話がある。いわゆるモノカルチャー経済である。選択し直せる選択肢を失って袋小路に入り込んでしまったという点が示唆的である。
人生でも事業でも、その時その時のフォーカスポイントを定めることはとても重要だが、それと同時に定期的に選択し直せるように選択肢を確保しておくことも非常に重要なのだ。
ソフトウェアエンジニアは人生において有力で魅力的な選択肢だと思う。私自身もそういう選択肢を常に持っていることは幸せだし、人生を充実させてくれるものだと確信している。万人に向いてるかどうかは分かりませんが、オススメです。
2024-11-03 22:24
当ブログのRSSを全件配信するようにした。Perl製OSSの拙作ブログエンジンであるところのRiji 側に手を入れた。ファイルサイズが大きくなるし、RSS分割を実装するのもめんどいので単純に直近30件配信にとどめていたが、今日日普通に1ファイルで全件配信して良いだろうと思い変更した。時代の流れで富豪的アプローチが許容される(?)よくある話。
ちなみに、全件配信しようと思ったきっかけは、ポッドキャスト「趣味でOSSをやっている者だ 」を始めるにあたって、Rebuild のRSSを観察したところ、全件配信しているのに気付いたので、じゃあいいか、となったというのがありました。
その昔の以下のnaoyaさんの19年前の記事で、RSS内に単独エントリの全文配信の是非について書かれているが、今や全件全文配信である。
RSSの全文配信をはじめました
Riji v1.1.1をリリースした
https://github.com/Songmu/p5-Riji/releases/tag/v1.1.1
ということで、実に2年10ヶ月ぶりのリリースとなった。最新のPerl 5.40.0で依存モジュールも最新化しても、ちゃんとテストもビルドも通るのが素晴らしい。Perlの後方互換を大事にする文化の賜物だと感じる。もちろんPerl自体の変化が緩やかになっていて、ライブラリの更新が活発にされることが減っているのも一因にあるとは思うけど。
Carmelとcpm導入して依存ロックした
https://github.com/Songmu/p5-Riji/pull/39
依存をバージョンロックしなくてもそんなに困っていなかったのだけど、ghcrに上げるコンテナビルドの再現性のために依存モジュールのバージョンをロックすることにした。令和だし。具体的には、Carmel を導入して、cpanfile.snapshotを作って、Dockerビルド時にはcpm でモジュールインストールするようにした。cpmがcpanfile.snapshotをちゃんと見てくれるので良かった。ちなみに、CPANに上げるtarballにはcpanfile.snapshotは含めないようにしている。
この辺のツールチェインがちゃんと動くのは嬉しい。このサイト構築に使っているコンテナもビルドし直せたので、まだまだ戦える。
緩やかに変化し続けること
ソフトウェアを数年放置してても、ちょっとメンテナンスすれば、ちゃんと最新に更新できるのは素晴らしい。Perlのエコシステム含めた変化が遅くなって、追随しやすくなっているという側面はあるが、Perl自体は毎年更新されて新バージョンがリリースされているので進化は止まっていない。
最近ソフトウェアの変化の速度について思うところがある。変化し続けることは必須だが、速すぎる変化はソフトウェアの寿命を縮めてしまうのではないか、当事者が燃え尽きやすくなってしまったり、追随できない人を振るい落としすぎてしまうのではないか、そんなことである。着実に変化・進化し続けられるラインを模索する必要がある。
Perlの使用をもはや積極的に勧めるものではないが、このRijiのように、普段は塩漬けにしておいて、数年に一回くらいお手入れをするくらいで使い続けられる、そんなソフトウェアもあって良いと思っている。
2024-10-15 01:37
https://crates.io/crates/r2sync
コマンドラインツールであり以下でインストールできる。
$ brew install Songmu/tap/r2sync
# or
$ cargo install r2sync
これはローカルディレクトリの中身をCloudflare R2に簡易的に同期するごく単純なツールで以下のように使う。
$ r2sync ./dir r2://your-bucket/path
リモートに同一ファイルが存在する場合にputをスキップするようになっていて、それが欲しくて作った。ちなみに、--public-domain というオプションを付けると、同一ファイルチェックを公開URL経由で行うようになってAPIアクセスを減らせる。
$ r2sync --public-domain files.example.com ./dir r2://your-bucket/path
ファイルの同一性チェックは、Content-LengthとETagを見ている。S3やR2はETagがコンテンツのMD5ハッシュ値なので、それで同一性チェックをしている。この挙動が未来永劫担保されるかわからないが、単にContent-Lengthだけ見るのも嫌だったし、実際にContent-Lengthだけ主に見ている aws s3 sync がたまにハマるという話も聞くのでそうした。
GitHub Actions
カスタムアクションも公開していて、以下のように使える。oss4.funでも導入した。
- uses: Songmu/r2sync@v0
with:
r2_account_id: ${{ secrets.R2_ACCOUNT_ID }}
r2_access_key_id: ${{ secrets.R2_ACCESS_KEY_ID }}
r2_secret_access_key: ${{ secrets.R2_SECRET_ACCESS_KEY }}
src: ./audio
dest: r2://<your-bucket>/audio
public_domain: files.example.com
作った動機
ポッドキャストの音声ファイルのアップロードをGitHub Actionsでやっているが、ディレクトリ内の全部の音声ファイルを毎回素朴にputしていたので流石に富豪すぎるので解決しようと考えたのが契機。
案外、既存の良いツールが見つけられなかったのと、aws s3 sync を使っても良かったのだけど、前述のETagの話もあったし、せっかくR2はエグレス料金が無料なのだからファイルの同一性チェックを公開URL経由でおこなうアイデアを盛り込んで作った。
Rust
習作がてらちょっとしたものをRustで作ってみたいと思っていたので、ちょうどよい題材だった。strとStringの使い分けとか、unwrapを使いすぎだったりとかまだまだお作法が分からない部分が多いが、とりあえずcrate公開までいけたのは良かった。Resultとかパターンマッチ含めた言語自体の書き味はかなり良い。
思っていたよりクロスビルド周りが難しくて、各プラットフォームにバイナリを提供するのに手こずった。とりあえず、GitHub Actions上で作るのは一旦断念して手元でバイナリをビルドしてGitHub Releasesにghr でアップロードするという一昔前のスタイルでお茶を濁した。
Rustを書き始めるにあたって「Rustの練習帳」が参考になった。Rustの考え方やコマンドラインツール作成について実践を通して学べる点で有益だった。Goでもこういう本があると良さそう(すでにあるかも)、とか思った。
オライリー・ジャパン
発売日 : 2024-01-18